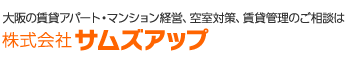大家さんの賃貸マンションを魅力的に見せる方法 2016年10月24日 9:33 PM
こんばんは!サムズアップの小西です。
前回のブログでは、大家さん自身の物件を好きになることが、たくさんの人に物件を知ってもらうことに繋がるとお伝えしました。
ただ、想いだけでは空室を埋めることはできません。
より魅力的な物件ほど成約率は高くなります。
そこで、今回は大家さんの物件をより魅力的に見せるためのポイントをお伝えします!!
****************************
1.写真にこだわる!
2.入居者の声を集める!
3.不動産業者に毎日訪問するときのコツ
まとめ
****************************
1.写真にこだわる!
入居者を募集する際、募集チラシ・ホームページ・賃貸情報誌などに物件写真はたくさん使われます。
しかし、多くの大家さんは、写真にほとんど工夫をしていらっしゃらないのが現状です。
大家さんの物件をより魅力的に見せるためには、お見合い写真のような「最高の一枚」を用意することが大切です。
もちろん、プロに撮ってもらうことが一番なのは間違いないのですが、費用がかかるので現実的ではありません。
しかし、ほんの少しの工夫で大家さん自身が写真を撮っても「最高の一枚」を取ることができるようになるのです。
では、ほんの少しの工夫を紹介していきます!!
①広角撮影可能なデジカメを用意する
→なぜ広角で撮影できるカメラが必要なのかというと、外観写真を撮る際、28mmくらいまでズームアウトしなければ建物全体が収まりません。
②斜め30~45度が物件のベストショットになりやすい
→多くの場合、30~45度と少し角度をつけるとベストショットになりやすいと言われていますが、同じ物件でも、正面・右・左と写真を撮る位置で見せてくれる表情は大きく変わります。大家さんの物件が一番魅力的に見える角度を見つけましょう!
③外観写真は逆光になりにくい時間帯に撮影する
→撮影する時間帯は、写真を撮るあなたの背に太陽がある時が最適です。もし、正面に太陽があると、逆光になって物件が黒く映ってしまいます。最近のデジカメは逆光機能がついていますが、やはり逆光にならない時間帯に撮る写真の方が一層魅力的に写ります。
④撮影は青空の生える晴れた日にする
→晴れた日は青空が背景になるので、より物件が映えるようになります。
これだけで物件の印象は格段に良くなります。
ただし、注意頂きたいのは、日光が当たっている場所は白飛びし、当たっていない場所は黒くつぶれることがあります。
撮影する位置を調整し、ベストショットになるまで取り続けましょう。
⑤室内写真は明るく撮るだけで印象がアップする
→明るくなるように照明をつけたり、日中に撮影するようにしましょう!
それでも、暗くなってしまうときはデジカメの露出補正機能を使って調整を行います。
お部屋を撮影する際も正面からだけでなく、部屋の角から対角に撮ると奥行きが出てきて良い写真が撮れます。
5つのポイントを紹介させて頂きました。
どれも大切なことで、全てを実践できれば閲覧数は増え、成約率は上がることでしょう。
しかし、紹介させて頂いたポイントを全て満たすことは意外に難しかったりもします。
なので、何枚も何枚も写真を撮ってください!!
そして、その写真を第三者、とくに女性に見てもらってください。
そこで気に入ってもらえた写真を使用しましょう。
というのも、物件を選ぶときの決定権を握るのは圧倒的に女性です。
大家さん好みの写真であっても、女性に気に入ってもらえなければ残念な写真で終わってしまいます。
なので、どれだけ写真に自信があったとしても、自分一人で決めることなく周囲の人にも聞いてみてください!!
2.入居者の声を集める!
入居者募集の際、強力な武器になるのが「入居者の声」です。
実際に住んでいる入居者の喜びの声があると、お客様に安心感を持って頂くことができるため、これ以上ない効果的な説得材料になります。
では、入居者の声をどのように集めましょうか?
話を聞いてもクレームが出てくるんじゃ…と不安な大家さんもいることでしょう。
でも大丈夫です!!
入居者の喜びの声を聞くことは条件さえ整っていれば、必ず聞くことができます。
その条件とは何でしょうか?
それは、「アンケート」を「入居の1カ月以内」に「入居者と顔を合わせて」実施することです。
アンケートは説明するまでもありませんが、なぜ「1カ月以内」で「顔を合わせてなのか」をご説明していきます。
1カ月以内にするのは、一番満足度が高いころだからです。
入居して長く住めば住むほど不具合が目立つようになりますし、満足度は時間の経過とともに下がってしまいます。
なので、一番満足度が高く一番好意的な声を集めやすい、この時期を狙いましょう!!
そして、顔を合わせる理由。
お分かりの方もいらっしゃるかもしれませんが、人は本人の目の前で悪いことは言えません。
つまり、大家さんの目の前で物件の悪い部分をハッキリと伝えてくる入居者は少ないということです。
また、「この物件のどこが気に入ったのか」とストレートに聞きましょう!
このように聞かれてマイナスの理由を考える人はまずいません。
気に入った理由を探して、答えてくれることが期待できます。
3.不動産業者に毎日訪問するときのコツ
毎日訪問する前に一つ大切なポイントがあります。
それは、大家さん自身と一緒に空室を埋めるために頑張ってくれる仲介会社を見つけることです。
たとえ、大家さんが毎日100件訪問したとしても、すべてが非協力的だった場合いつまで経っても空室は埋まらないでしょう。
つまり、協力的な会社を10件見つける方が重要なのです。
それを見つけるためには、かなり多くの仲介会社を回ることになってしまうかもしれませんが。。。
そんな協力的な会社が見つかれば、定期的に営業訪問をして関係性を深めていってください!
営業パターンとしては、金曜日(週末)に募集チラシを渡し、大家さんと物件を知ってもらいます。
そして、週明けの月曜日に週末のお客様の動きや反響を電話、もしくは訪問して聞きましょう。
もし、反響が思わしくないなら、募集条件を見直したり、募集チラシを修正してみるべきです。
そして、金曜日までに新しいチラシを送り、反響が得られるように仲介会社に電話、もしくは訪問していきます。
これを1つのサイクルとして、入居者が決まるまで継続していきます。
この中で注意すべきなのは、何十分も話し込まないこと。
仲介会社の営業マンも忙しくしています。
そんな中で、毎週長い時間話し込まれると良い思いはしません。
空気の読めない大家にならないためにも、挨拶は短く、1~2分程度で帰りましょう。
営業トークをしなくても、大家さんの訪問目的は営業マンに伝わっています。
それだけで十分なのです!!
まとめ
物件を魅力的にするためには、面倒なことが多いな…と感じられた方も多いのではないでしょうか。
そんな簡単に満室経営を実現することは難しいことだとお分かり頂けたのではないでしょうか。
もちろん、誰もが住みたくなるような物件にリフォームをしたり、家賃を下げたりすることで入居付けをすることはできるでしょう。
ただ、それだけリフォームに費用をかけれる方は少ないです。
家賃を下げることで入居者の属性が下がる可能性もあるので、家賃を安易に下げることはオススメしません。
「継続は力なり」です!!
コツコツ積み重ねていきましょう!!!
いよいよ次回からは、内見時に成約率を上げるためにできることをご紹介していきます。
ではまた!次回のブログでお会いしましょう!!
大家さんの賃貸マンションをお客様に知ってもらうためにできること 2016年10月23日 2:01 PM
こんにちは!
サムズアップの小西です。
前回までのブログでは、お部屋に少し工夫するだけで成約率を高めることができるとお話させて頂きました。
しかし、どれだけ良い物件にしたとしても、入居希望者に見てもらえなければ元も子もありません。
今回は大家さんの物件を効果的かつお金をかけずにPRすることができるのかお伝えしていきます!!
******************************
目次
1.物件情報は3大ポータルサイトに登録!!
2.閲覧数を上げる!!
3.募集チラシを自分で作る!!
******************************
1.物件情報は3大ポータルサイトに登録!!
あなたの物件はインターネットに掲載されていますか?!
今ではインターネットがすっかり普及してしまったことにより、入居者自らが物件を探すことができるようになりました。
つまり、ネットに掲載していない物件は市場という土俵に乗ることさえできていないといっても過言ではありません。
そんな時は、募集を依頼している不動産業者に連絡して、【ホームズ・スーモ・アットホーム】に掲載してもらうようにしてください!
この3大ポータルサイトに登録さえしていれば、yahoo!やGoogleなど大手情報検索サイトと連動しているため、より多くの人にあなたの物件を見てもらうことができるようになります。
ここで一つ注意して頂きたいのは、インターネットに掲載していれば絶対安心というわけではないということ。
山ほどある物件情報の中から、簡単に大家さんの物件を見つけてもらうことはできません。
その中で、特に重要であろうポイントを5つ挙げていきます。
①いくつの大手ポータルサイトに掲載されているか?
②あなたの物件がどれくらい閲覧されているか?
③競合物件と比べて設備や仕様、賃料や条件とのバランスはどうか?
④物件の内外の写真はエレガントかつ最大数まで掲載されているかどうか?
⑤担当コメントが入力され、かつ魅力的なPRコメントになっているかどうか?
2.閲覧数を上げる
1.3大ポータルサイトに登録する!!で5つポイントを上げさせて頂きましたが、成約率を高めるためには閲覧数をどう増やすのかが一番大切なことになります。
では、どうやって閲覧数を増やせばいいのでしょうか?
それは、上記でも挙げた物件の写真や担当のコメントです。
写真の見た目が悪かったり、間取り図面すら掲載されていない物件は、入居者に振り返ってもらうことはできないでしょう。
ちなみに閲覧数は仲介業者に聞けば教えてくれるので、定期的にチェックしてみてください。
もし反応が落ちているときには、PRコメントや条件を変えたりして、閲覧数を増やすことを考えてみてください!!
競合物件と大家さんの物件を比較して、条件を変更してみること。
大家さんの物件が一番魅力的にみえる写真にしてみること。
担当コメントを魅力的なものにすること。
ちょっと一工夫加えるだけで、閲覧数は大きく変わります。
簡単にできることばかりなので、是非一度お試しください!!!
3.募集チラシを自分で作る!!
募集チラシは大家さん自らが作ることによって、その広告効果を最大限に発揮します。
不動産業者に広告を任せてしまうと、お決まりのフォーマットと文言でしか大家さんの物件は紹介されませんし、毎日たくさんの物件を取り扱っているのでこだわったチラシを作ることもできないからです。
しかし、自分の物件の良さを一番知っている大家さん自身が作成すれば、個性ある魅力的な広告を作成することが可能になります。
大家さん自らが作成された募集チラシは、入居希望者ではなく、不動産会社への営業でこそ最大の効果を発揮することになるのです。
また、入居募集に関しては、できるだけ間口を広くすることが重要です。
入居募集依頼を一社だけに任せるのではなく、数多くの不動産会社に依頼することが重要ということです。
自作チラシを不動産会社の担当者に渡せば、営業マンが新たに広告を作成する手間が省けるだけでなく、大家さん自身と物件を営業マンに強力に印象付けることもできます。
なかには、大家さんの熱心さが伝わり、積極的に募集活動を行ってくれるケースもあります。
なので、募集チラシはご自身で作成し、ご自身で不動産会社の担当者に私に行くことをオススメします!!!
では、どんなチラシを作ればいいのか。そう思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
簡単にご説明していきます!
まず、これまでに使っていた物件チラシを用意してください。
この中から、新たなチラシに使える間取りや物件概要、写真などを切り取ってください。
次に、物件のセールスポイントを思いつくままに書き出してください!
「キッチンは独立型!扉で仕切ればリビングから見えません!」
「IHコンロなので火を使わず安心!!」
このように簡単なもので構いません。必ず大家さんの物件にもセールスポイントはあります。
この機会に、物件のセールスポイントを考えてみるのもいいのではないでしょうか。
使う言葉が決まれば、文字の大きさや書体を目立つように編集します。
これはパソコンでも手書きでもどちらでも構いません。
大家さんがやりやすい方でやってください。
あとは、物件のイメージに合ったイラストを貼り付けましょう!
イラストの間に手書きの言葉を入れると非常に親しみやすく目につきやすいチラシになるので、ここはこだわっていきましょう。
最後に、完成した台紙をコピーすれば手作りチラシの完成です!!!!
まとめ
ネットと広告を上手に活用することで、たくさんの人に物件を知ってもらえるということが少しだけでもお分かり頂けたのではないでしょうか。
物件に対する想いが強ければ強いほど、不動産会社や入居など、たくさんの人に振り向いてもらいやすくなります!!
次回はより魅力的に物件を紹介するには何ができるのかをご紹介していきます!!
賃貸マンションの空室が埋まるリフォーム術 2016年10月22日 7:19 AM
おはようございます!小西です!
前回のブログでは、マンションの外観や共用スペースのイメージを変えることが、内見者の成約率を高め、既存の入居者の満足度を高めるとお話させて頂きました。
本日は、気になる部屋のイメージを良くする方法をお伝えしていきます!!
****************************************
目次
1.部屋のイメージはアクセントクロスで変わる!!
2.年代物のユニットバスでも大丈夫!!
3.壁紙は入居者に選んでもらえ!!
4.リフォームにどこまでお金をかけるべき?!
****************************************
1.部屋のイメージはアクセントクロスで変わる!!
お部屋の壁は、お金をかけずにイメージを良くすることができるので、費用対効果の高いです。
真っ白な壁でも、1か所もしくは1面だけをアクセントカラーとしてワンポイントクロスを貼ることで、ぐっとおしゃれな印象にすることができます。
しかし、やってみると意外にクロスの色やデザインの選定が難しく、なんとなく無難なものに落ち着いてしまい、効果が出ないこともありますし、反対に奇抜にしすぎて入居者から嫌われてしまうこともあります。
デメリットがあることを否定はしませんが、印象をよくするためにできることはあります。
それは、お部屋のコンセプトをハッキリとさせることです。
どんな人に、どのような生活をしてもらいたいのか。
これを明確にすることで、どのようなクロスを貼るべきなのかも明確になります。
たとえば、新婚さんや若いカップルに入居してほしいなら、ピンクの縦縞柄のアクセントクロスを使用し、エレガントで明るい清潔感を演出します。
その他にも、一面をオレンジや黄色にすれば温かみのあるアットホームな部屋を演出できますし、ブルー系のアクセントクロスを使用することでクールで都会的な部屋を演出することができます。
また、入居者自身に壁紙を選んでもらう方法もあります。
自分の好きなクロスを使用することで、入居者に愛着を感じてもらうことが狙いです。
自分好みの部屋にカスタマイズしてもらえる優越感、ワクワク感が成約率をアップさせ、長期的な入居に繋がるのです。
その場合は、内見して頂く部屋にクロスのカタログを展示して、変更していい部分やおよその面積を決めて、その場で選んでもらいましょう!!
2.年代物のユニットバスでも大丈夫!!
リフォームをする際に、最も気になるのがユニットバスではないでしょうか。
長年使っていると、石鹸カスや湯垢、変色などが気になることも多いです。
どこにでもある標準的なユニットバスは手軽に新品に入れ替えることができないので、どうしてもイメージアップしにくいポイントでもあります。
もちろん、浴室ぜんたいを塗装して新品同様にできる技術もありますが、コストが高く費用対効果としてはあまりメリットはありません。
しかし、浴室をほんのちょっとのリメイクで高級感を演出できる方法はあります。
古くなったユニットバスの壁にアクセントシートを張るのです。
通常のユニットバスは壁面が全部白色で、ありきたりなものばかりです。
なので、壁面にアクセントシートを張ってみてはいかがでしょうか。
貼るシートは種類も値段も様々ですが、木目調のシートがオススメです。
このシートはエレベーターの扉などにも貼られてることが多く、質感が非常によく見栄えが良くなります。
シートの寿命自体は5~7年くらいですが、5年後に違うシートに張り替えればいいので、あまり高耐久にこだわる必要はないでしょう。
もし本格的なユニットバスのリメイクを行うとすると、大体20~30万円ほどかかります。
しかし、アクセントシートを貼る方法なら、工事費用も3~5万円程度で施工でき、見た目はホテルのようになるので非常にリーズナブルです!!
3.壁紙は入居者に選んでもらえ!!
先ほどもご紹介させて頂きましたが、入居者に好みの壁紙を自由に選べるオプションを設けることで、新規入居者の獲得につなげる大家さんも増えています。
入居者は壁紙を選ぶのにかかる費用を負担しなくても、自分好みの部屋にすることができるので、効果的な空室対策として期待できます。
選べるクロスは、原状回復の範囲で選ばれる壁紙ではなく、分譲住宅に採用されるサンプル品の中から選んでもらうといいでしょう。
分譲マンションに採用されるサンプルのほうが、デザイン、色味ともに様々なサンプルが用意されていて、選ぶ楽しみが格段にアップします。
さらに、仕上げに高級感が出るので、部屋自体のグレードを高めることができ、入居者の満足度も確実に高まります。
2つの価格差は㎡あたり300円程度なので、ワンルームを全部サンプルにしても3~5万円程度のコストアップにしかなりません。
入居者好みの部屋に仕立て上げることで、長期入居に繋がり、費用対効果は大きくなります。
4.リフォームにどこまでお金をかけるべき?!
いざリフォームをするとき、採算を度外視して無尽蔵にお金をかけるわけにはいきません。
リフォームをしても、家賃ンは2倍になるわけではありません。
とはいえ、お金のかけなさすぎもダメです。
一般的な原状回復程度のリフォームでは、逆に空室期間が伸びてしまい、家賃下落の負のスパイラルに陥ってしまう可能性もあります。
では、リフォームにはいくらまでかければいいのでしょうか??
私が知っている限りでは、家賃の6か月分をかける大家さんが多いです。
これなら空室で困っている大家さんでも、何とか捻り出せる予算だからです。
ここまででご紹介させて頂いたリフォームも、これだけの予算があれば十分まかなえるでしょう。
かといって、6か月分にこだわる必要もありません。
家賃2年分をかけ、3年目から利益を得れるようにリフォームをする大家さんもいます。
反対に3か月分をかけてリフォームをする大家さんもいます。
リフォームコストの掛け方は人により様々ですので、大家さん自身がマンション経営をどうしたいのかを考えられた上で、リフォームをすることが一番です。
ちなみにですが、外装にかけるリフォームの予算は、塗装のみであれば建物全体の家賃の1~3か月分程度を基準に考えるとよいかと思います。
リフォームの費用にいくらまでかけるべきか悩んだ時には、この考え方を参考にしてください!
ここまでのノウハウを実践すれば、大家さんの物件の商品力はアップしていることでしょう。
商品力を高めることが出れば、次はその商品をどう効果的かつお金をかけずにPRできるかが重要です。
次回のブログでは、成果の上がっている効果的な募集戦略についてお話していきます!!
リフォームが空室対策になる理由 2016年10月21日 8:29 AM
おはようございます!サムズアップ小西です。
前回のブログでは、マンションの空室ができてしまう原因について紹介させて頂きました。
本日から数回に分けて、満室経営を実現している大家さんが実践している空室対策をご紹介していこうと思います。
*************************************
目次
1.小予算でおしゃれ!ときめきリフォーム術
2.いま人気の設備はつけない!!
3.外観イメージを変える!!
4.エントランスのリフォームはケチらない!!
*************************************
1.小予算でおしゃれ!ときめきリフォーム術
空室対策の一番のポイントは、仲介業者に「客付けさせてほしい!」と言われるような物件にすることです。
そうするためには、内見したら即制約するような物件にする必要ことが必要です。
しかし、多くの大家さんの物件は、残念ながら仲介業者が客付けしたくなるような物件にはなっていません。
むしろ、「家賃を下げないと決まらない・・・」と思われてしまっているメンテナンスの行き届いていない物件のほうが多いといっても過言ではありません。
では、仲介業者が紹介したいと思う物件はどんなものなのでしょうか。
それは家賃以上の価値を感じられる物件になっているのかどうかです。
端的に言うと、入居者に設定家賃以上の価値を感じてもらうことができれば、需給状況など関係なく、どんな家賃でも入居者は決まるものなのです。
入居者が決まらないというのは、その家賃に見合った価値を提供できていないということなのです。
では、家賃以上の価値を感じてもらうためにはどうすればいいのでしょうか。
答えはとてもシンプルです。
リフォームして失われた商品価値を取り戻すしかありません。
ここで注意して頂きたいことがあります。
ただ単にリフォームをして商品価値を取り戻すだけではいけません。
採算に合う程度のお金をかけてリフォームをすることが重要です。
そして、重要なことはもう一つあります。
「こんなものがあったら便利だな」という生活アイテムを散りばめることです。
和室を洋室にリノベーションしなくても、ほんの少しのアイデアで商品力をアップさせることは可能になるのです。
それでは、これから小予算でおしゃれなリフォームをお伝えしていきます!!
2.いま人気の設備はつけない!!
見出しを見て、少し意外に感じられた方も多いのではないでしょうか。
ではなぜ、いま人気の設備はつけないほうがいいのか。
それは、いま人気の設備を付けたとしても、数年後にはブームが去ってしまっているからです。
たとえば、東日本大震災前には人気設備の上位にあったオール電化は、今では電力供給の不安から人気が落ちてきています。
他にも防犯性が高いと言われるカードキーや携帯で施錠が可能なハイテクキーなども、一時的には人気がありましたが、現在では普通の鍵の物件と家賃や入居率に差がつくことはなくなりました。
ただし、注意して頂きたいのは、絶対に必要なアイテムを外さないこと。
たとえば、防犯対策としてのモニター付きインターホン。
女性の大半は、防犯面からモニター付きインターホンのない物件には住みたくないという事実があります。
このような絶対に必要なアイテムは、全国賃貸住宅新聞社が定期的に発表している賃貸設備人気アンケートを参考にしてみてはいかがでしょうか。
しかし、これから先につけておくべきアイテムを上記のランキングから知ることはできません。
アパートの商品価値を高めていくためには、将来を先取りした設備を知る必要があります。
では、どうすれば将来を先取りすることができるのでしょうか。
ひとつご提案させて頂くと、最新分譲マンションの設備を参考にするということ。
実は、賃貸物件の人気設備は、分譲マンションの人気設備が数年後に波及してきていることがほとんどなのです。
分譲マンションは販売競争に勝ち抜くため、世の中のトレンドを先取りした設備で勝負しています。
つまり、常に賃貸物件の数年先をいっている分譲マンションの設備を見ると、将来、賃貸物件で人気が出る設備が分かるようになるのです。
3.外観イメージを変える!!
人の第一印象は、出会った瞬間に決まると言われています。
同じように、マンションも内見時の第一印象で物件の印象が決まっているのです。
物件の第一印象が良ければ、物件への期待度も高まり、おのずと成約率は高まります。
つまり、見た目の印象をよくすれば、どんなに古い物件でも入居率を改善することができるようになるのです。
それだけマンションの外観は大切なわけですが、意外にも外観にこだわる大家さんは少ないです。
ところで、外観のイメージを変えるといっても、どうすればいいのでしょうか。
第一印象を意識して外観を変えるなら、色を工夫してみましょう!!
なぜなら、人が第一印象を決定するとき、視覚から得られる情報が約90%を占めているからです。
その中でも、55%を色で、45%を形で判断していると言われています。
つまり、色を工夫すれば第一印象を良くすることができるわけです。
ただ、色選びって難しいんじゃないの?と疑問に感じられた方もいることでしょう。
しかし、色選びに特別な感性やセンスは必要ありません。
ポイントとして、配色の基本は2~3色以内におさえること。
基本はメインの色が1色、アクセントカラーが1色あれば十分にイメージを変えることができます。
面積比率としては、メインの色が全体の70%、アクセントは鮮やかなものは5%程度、ダークな色であれば30%程度まで配色しても問題ありません。
4.エントランスのリフォームはケチらない!!
先ほど入居率は第一印象が大きくかかわっているという話をさせて頂きました。
内見者が最初に目にするものが外観なら、次に目に飛び込んでくるのはエントランスです。
エントランスは物件の顔ともいえる重要な部分なので、常に清潔にしておく必要があります。
ここで悪い印象を与えてしまうと、「部屋の中も汚いんだろう」と想像されてしまうこともあります。
反対にエントランスがきれいだと、気持ちよく内見者を迎えることができますし、部屋への期待も膨らませてもらうことができます。
郵便受けをA4サイズの郵便物も入るダイヤルロック式に取り換えたり、エントランスの壁と天井を振りなおして清潔感と明るさを出すことも有効的でしょう。
ほかにも、季節ごとにエントランスを飾り付けて演出することも非常に有効です。
例えば、クリスマスにはクリスマスツリーを置いてみたり、お正月には鏡餅を置いてみたり。
しかし、これらは物件のすぐ近く住んでいないとできないことではあります。
遠方に住まれている方にオススメなのは、人工植物やフェイクフラワーです。
見た目を良くすることが目的なのですから、本物の植物にこだわる必要は全くありません。
お手入れもラクで、いつまでも綺麗なままエントランスを彩ることができます。
このように、ときめきと癒しのエントランスを演出できれば、成約率が上がるだけではなく、既存の入居者の満足度も上がり長期的に入居して頂くこともできるようになります!
大家さんの賃貸マンションに空室ができる理由 2016年10月20日 9:10 PM
こんばんは!サムズアップの小西です!
長らくブログの更新お休みさせて頂いておりました。。。
これまでブログをお読み頂いていた読者のみなさまには、大変ご心配をおかけしました。。。
本日より北岡に代わりまして、小西がブログを更新していきます!!
お休みさせて頂いた間にも、たくさんの空室対策やリノベーションのノウハウを学んでおりますので、今後のブログにも是非とも期待してください!!
さて、再開第一弾のテーマは空室ができてしまう理由についお話していきたいと思います。
マンションをお持ちの大家様は空室に悩まれていることが多いのではないでしょうか?
大家様とお話させて頂く中で、「空室が埋まらない」「家賃が下がっている」などたくさん話をお聞きします。
そこで今回は「満室経営」を実現している大家さんが実践していることを紹介させて頂きます。
****************************
目次
1.なぜ空室ができるのか
2.自分の物件の強みと弱みを知る
3.家賃は下げてはいけない!!
****************************
1.なぜ空室ができるのか
言うまでもありませんが、賃貸経営にとっての最大のリスクは「空室」です。
入居者がいなければ、賃貸経営は成り立ちません。
では、空室問題を生み出しているものは何でしょうか。
それは「供給過剰」と「少子化」です。
人口が減少する一方で、年間約90万戸の住宅が新築されています。
今後も日本の人口は減少し続けることが予想されています。
2004年の1億2700万人をピークに人口は減少し続け、2030年には1億1552万人、2050年には1億人を切り9515万人とまで推計されています。
ピーク時と比べると、46年間で3200万人も減少しています。
1年平均にすると約70万人の減少。
この数字は島根県の人口に匹敵しています。
つまり、毎年、島根県1県分の人口が消失していると言えます。
このように、住宅需要が減り続ける中で、供給はこれまで通りなのですから、空室が増え続けてしまうのです。
その結果、今では5戸に1戸が空室の時代になってしまいました。
2.自分の物件の強みと弱みを知る
空室対策を始めるとき、必要となるはじめの一歩は、いったい何だと思いますか?
それは自分の物件の強みと弱みをよく知ることです。
客観的に自分の物件の強みと弱みを知ることができれば、自分の物件のどこをさらに伸ばし、どこを克服すればいいのかが明確になります。
こうすることで物件力を効率的に高めることができ、早期満室が実現することになるのです。
では、具体的に何をしていけばいいのでしょうか。
1つ目は、周辺環境を知ること。
周辺環境を知ることで、自分の物件の位置づけが分かります。
その地域の市場で自分の物件がどのような層に選ばれる可能性があるのか、周辺環境がどのように物件の価値向上に寄与しているのか。
ターゲット層に選んでもらえる物件になるのかが分かります。
2つ目は物件そのものを知ること。
つまり、同じ家賃相場、同じ間取りであれば、自分の物件のどこがライバルに勝っていて、どこが劣っているのかを明確にすることができます。
そして、それぞれを伸ばし、克服していけば、必ず勝てる物件に進化させることができるようになります。
これらを、大家さん自身が物件を正確に把握していなければ、遠くからわざわざ部屋を探しに来る入居者に物件の良さを伝えることはできません。
周辺環境や物件そのものを知る時は、大家さん自身が入居者の目線になって、くまなく近隣環境を調べる必要があります。
3.家賃を下げてはいけない!!
空室が埋まらないと、管理会社から家賃を下げるように言われることも多いです。
しかし、そう簡単に家賃を下げてはいけません。
家賃を下げるのは、あくまでも最後の手段です。
まず、家賃を下げる前にどんな手があるのでしょうか。
リノベーションをして物件の価値を上げること。
空室にポップをつけて内見者に良いイメージを持ってもらうこと。
募集チラシを作って不動産会社にもっていくこと。。。
できることはいくらでもあります。まずはできることをすべてやってみましょう。
家賃を一度下げてしまうと、再び上げることがかなり難しくなってしまいます。
なので、もう万策尽きたというところまで「値下げ」という最終手段はとるべきではありません。
今日は空室になってしまう原因について、お話ししました。
リフォームや募集戦略については、次回以降のブログで詳しくお話させて頂きます!!
経営の極意~建物管理のポイント~ 2014年7月11日 9:30 AM
・木造
木造アパートにおいては、目視が中心となります。
木造の部分的な鉄部に関しては、以前にご説明した
ものと同じです。周期は6年が目安となります。
建物本体については、瓦が割れていないかの確認が
必要です。瓦が割れていたり、また、その接着剤が劣化
していると雨漏れの原因になりかねません。
外壁については、材料によります。築30年以上の建物で
多いのが、塗り壁です。塗り壁の場合は、外壁面にクラック
(ひび割れ)が入っていないか、手で表面を触ったときに
色がついてこないか、などのチェックが必要です。
クラックがあると、これも水漏れの原因となる場合が多く
あります。
観点は変わりますが、木造アパートで問題になるのが、
耐震問題です。これは、劣化とともに増々危険な状態に
なってきます。
また、劣化以外にも目視でチェックするだけで、その危険性が
分かるポイントがありますので、ご紹介いたします。
経営の極意~建物管理のポイント~ 2014年7月10日 9:29 AM
・鉄骨造
鉄骨造は他構造の建物とチェックするポイントが変わって
きます。
特に注意すべきポイントが“コーキング”です。鉄骨造でも
特に外壁をALCで仕上げている建物は注意が必要です。
この構造の場合、外壁材(ALC)を接合しているのは
コーキングです。一般的なコーキングは経年と共に劣化
していきます。特に風雨や日光にさらされる箇所については
劣化が著しいです。このコーキングが痩せて割れてくると、
雨漏れの原因になります。
また、その外壁材自体も日光が直接当たるような場所では、
劣化が進み、割れてきます。その割れから外壁材の中に
水が回ると、中の金属が錆びて大変なことになります。この
外壁材も指で触って粉のようなものが指に付着すると、劣化が
進んでいるということになります。
あとは、鉄部などは他構造の建物と同じようにチェックが必要
です。
今では、このようなALC材でも長寿命のコーキングや外壁材と
コーキングの上から塗る塗料で、長寿命の材料がいくつか
出ています。修繕の際は、そのような工夫をすることで建物を
より良い環境で維持管理していくことができると思います。
経営の極意~建物管理のポイント~ 2014年7月9日 9:28 AM
次は屋根です。屋根は本来、防水処理をしています。この
防水処理も様々であり、シート防水やウレタン防水など
施工方法は色々あります。屋根は特に日差しが直接あたり、
風雨にさらされる場所でもあります。ですので、防水が割れたり、
膨らんだりして、そこから水が廻り、躯体を劣化させるという
ことに繋がっていきます。防水材が破れてたり、膨らんでいると
補修を考えるタイミングだと考えられます。
次に外壁やサッシ廻りの目地です。ここには本来コーキングと
言われるもので防水処理されています。これは施工当初は
弾力のある素材ですが、日光や風雨の中で経年と共に硬化して
きます。また、年数が経つにつれて収縮してきて、やせ細って
きます。そうなると、その隙間から水が入って躯体に影響を
与えるとか、室内への水漏れの原因となります。チェックする
ときは、目地材を指で触り、指に白い粉が付着すると修繕の
タイミングです。これが悪化すると、指で触っただけで、ボロボロと
落ちるような状態になります。ここまでいくと漏水がいつ起きても
おかしくない状況です。ですので、そうなる前に対処が必要です。
あとは、構造に関係してこないのですが、鉄部です。例えば、
階段手摺やパイプスペース扉、玄関枠、共用灯の台座などが
代表的なものとして挙げられます。
表面的な錆であればサンドペーパーなどで表面の錆を落とし、
錆止め、仕上げと塗れば復旧しますが、これが鉄の中まで
腐食しているとそのような補修では復旧できません。鉄部を
守るという意味でも、また入居という意味でも鉄部のチェックも
大切になってきます。
経営の極意~建物管理のポイント~ 2014年7月8日 9:27 AM
建物管理のポイントについて詳しくみていきます。
①躯体の劣化度については、大きく構造に分けて3つの
見方があります。
・鉄筋コンクリート造
鉄筋コンクリート造の場合、大切なことが躯体(コンクリート)
の中に水が入らないことです。コンクリートの中には鉄筋が
入っており、その鉄筋まで水が廻ると、鉄筋が錆、膨張して
コンクリートを内側から破壊してしまうリスクが高くなります。
どこから水が入るかというと、クラック(ひび割れ)です。
クラックにも様々ありまして、割れの細いヘアークラックと言う
ものから、大きな割れで致命傷尾に至るものまで様々です。
ヘアークラックであれば、躯体に対して大きな問題はありませんが、
大きなクラックは、そこから水が浸透する可能性が高いと
思われます。
次に、軒裏の腐食です。バルコニーの裏側や共用廊下の天井
などがそこにあたります。特にバルコニーなどは防水処理を
行っていない建物もありますので厄介です。これも躯体に水が浸透
すると、劣化の原因となります。目視で白く変色していたり、
水の跡が残っていれば、補修をする必要があります。
外壁にタイルを張っている場合には、そのタイルが浮いていないか、
ということも大切です。これは、金属でタイルの表面をなでるように
叩くと、高い音がする箇所が出てきます。それはタイルが浮いて
いる証拠です。タイルが落ちて入居者さんや通行人に怪我を
させると大変なことになりますので、張り替えるなどの対応が
必要になります。
経営の極意~建物の価値には“経年率”がかかる~ 2014年7月7日 9:26 AM
これまでの建物管理では運営はできない、と考えています。
建物管理というと、定期清掃や日常清掃、各種法定点検などを
思い浮かべると思います。確かに、間違ってはおりませんし、
これらのことは重要な要素です。
しかし、建物というのはそれだけでしょうか。他に維持、管理する
べきものはないのでしょうか。あるんです。
建物の構造によりチェックするべきものは変わってきますが、大部分は
変わらないものです。
(建物チェック)
①躯体の劣化度
・鉄筋コンクリート造:白華現象、タイル浮き、割れ、コーキング目地、屋上防水など
・鉄骨造:ALC目地・サッシ廻りコーキング、ALC劣化など
・木造:外壁塗り材の劣化、屋根(瓦)割れなど
②配管(給水、排水)
➂共用設備(EV・ポンプ・受水槽・共用灯など)
などが主なものとしてあげられます。
では、これまでの賃貸管理(建物管理)でここまでチェックし、
アドバイスをしてくれる管理があったかと言うと、少ないと思います。
これは、入居が決まる決まらないという話ではなく、その建物自体の
価値、運営に関わることになってきます。
ですので、建物管理をしていく中で、必要不可欠な要素になって
くるのではないでしょうか。